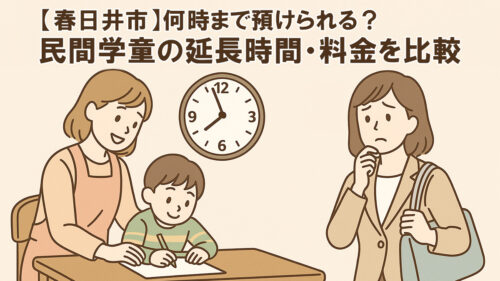小1の壁は学童で突破できる?子どもの成長を促進する選択肢
2025年04月21日

4月に入り、新1年生として生活がスタートしたご家庭が直面する「小1の壁」。
子どもが小学校に入学すると、それまでの保育園生活とは大きく環境が変わり、親の働き方や家庭の生活リズムにも影響を及ぼします。特に共働き家庭にとっては、早い下校時間や長期休暇中の預け先の確保など、多くの悩みが一気に押し寄せてくるタイミングです。
そんな中、学童保育に入会させるご家庭も増えてきています。今年は特に入会希望者も多く、学童保育の需要も高まっています。本記事では、小1の壁を乗り越えるために、学童保育がどのように役立つのか、そして、学童を上手く活用するためのポイントについて解説していきます。
小1の壁とは?なぜ多くの親が直面するのか
「小1の壁」とは、子どもが小学校に入学することで、それまで保育園で成り立っていた家庭と仕事のバランスが崩れ、保護者が働き続けることに困難を感じるようになる現象を指します。具体的には下記のような壁に直面するご家庭が多く存在します。
保育園と小学校の「預かり時間ギャップ」
保育園では朝早くから夜遅くまで預けられる体制が整っていましたが、小学校では授業が終わるのが早く、14〜15時には下校します。放課後や長期休暇の対応が必要になるため、フルタイムで働く親にとっては大きなハードルとなります。
親のサポートが急に増える現実
学校生活では子どもが自分でやるべきことが増える一方で、実際には親のサポートも必要になります。宿題の確認、提出物のチェック、朝の準備など、地味ながら毎日続く負担が親にのしかかります。
周囲の協力を得にくく、家庭だけで抱え込んでしまう
保育園時代は、保護者同士や先生との関わりが密で、困ったときに相談しやすい環境が整っていました。しかし、小学校では保護者の交流機会が減り、先生との接点も限られるため、孤立感を感じるケースが少なくありません。
また、祖父母など家族の支援が受けられない状況にある家庭では、子どもを預けられる場を自分たちで確保する必要があります。地域によっては放課後の選択肢が限られており、「誰にも頼れず、自分で何とかしなければならない」というプレッシャーが、小1の壁をさらに高くしているのです。
小1の壁を乗り越えるために学童を活用する6つのメリット
1. 夏休みや臨時休校に対応できる
小学校は保育園に比べて休みが多く、特に夏休みや冬休みなどの長期休暇、インフルエンザ流行による学級閉鎖や臨時休校といった予測できないスケジュール変更がたびたび発生します。こうした期間中、子どもをどう過ごさせるか悩むのが保護者にとっての大きな小1の壁と言えます。学童保育では、こうした長期休暇や急な休校にも対応してくれるところが多く、安心して仕事を続けることができます。
2. 安心して仕事ができる
小学校の下校時間は早く、長期休暇も多いため、フルタイム勤務の家庭にとっては放課後の過ごし方が大きな課題です。誰もいない家に一人でお留守番をさせると「怪我をしていたらどうしよう…」「体調が悪くなっていたら…」と様々な心配事が頭をよぎり、仕事に集中できないという小1の壁にぶつかる親御さんも少なくありません。学童に通わせることで、子どもを安全に預けられる環境が整い、仕事と子育ての両立がしやすくなります。
3. 家族全体の生活リズムが整う
学童ではおやつの時間や学習時間が決まっているなど、ある程度決まった日課があります。これにより、家庭での「だらだら時間」を防ぎ、早寝早起きや宿題の習慣など、健やかな生活リズムが自然と身につきます。子どものうちからつけた習慣は大人になっても引き継がれていくものです、小1の壁を乗り越え、健康に育ってもらうためにも習慣には注意しましょう。
4. コミュニケーションの場が増える
学童は、他学校の生徒や異年齢の子どもたちとたくさん関わる機会があります。そのため、学校の友達や先生以外にも、コミュニケーションをとる機会を増やすことができます。コミュニケーションをたくさん取っておくことで、思いやりや助け合いの気持ちが生まれ、集団の中での振る舞いを学ぶことができるので、お子さんを一歩大人に近づけることができます。
5. 自立心が芽生える
学童では、学校同様に、自分のことは自分でやるというスタイルが基本です。荷物の整理や宿題への取り組み、時間の使い方など、小さな積み重ねの中で少しずつ自立心が育っていきます。更に、自分一人でできることを早めの段階で増やしていくことができます。そのため、学校での取り組みが苦に感じなかったり、得意げに主体性を持って行動してくれる姿が見られるかもしれません。お子さんが宿題になかなか取り組まずに時間に追われて小1の壁を感じている親御さんにはピッタリの選択肢だといえます。
6. 家庭ではできない体験ができる
工作や運動などは学校でも学ぶことができます。しかし学童では、季節ごとのイベントやレクなど、家庭ではなかなか実現しにくい体験が用意されています。数々の行事を通して季節ごとのイベントの知識を得たり、レクを通じて子どもたちの創造力や主体性を育むチャンスを掴めます。また、異年齢の友達と一緒に活動することで、自然とリーダーシップや思いやりの心も養われるので、身のある経験を増やすのには最高の機会です。
正しい学童の選び方とチェックポイント4選
子どもが安全に過ごせそうな環境
まず、一番重要視したいのが施設内の安全体制です。例えば、子ども出入りがしっかりと管理されているか、緊急時の避難訓練が定期的に行われているかなどは重要なチェックポイントです。また、子どもの人数に対して、何人のスタッフが付いているかも重要です。予想外の出来事にも対応できるように極力少人数につき一人のスタッフが付いている学童を選ぶことをおすすめします。
利用時間や休暇対応が家庭に合っているか
働く保護者にとって、学童の利用時間や柔軟性も重要になります。平日の預かり時間や延長対応や夏休み・冬休みなど長期休暇中にも利用可能かなど、自分たちのライフスタイルと無理なく両立できそうかを必ず確認しておきましょう。対応時間が勤務体系とズレていると、かえって不便に感じてしまう可能性があります。
教育内容が充実しているか
学童ごとに1日の過ごし方も学び方も大きく異なります。宿題に取り組む時間がしっかりと設けられているか、自由遊びの時間にバリエーションがあるか、それ以上に収穫のある時間が用意されているかなど、学童のカリキュラムによって子どもの充実度や知識量も大きく変わってきます。単に時間を過ごすだけではなく、子どもにとって身のある時間になるかを考えましょう。
保護者との連携ができているか
小学校に入ると子供の様子が見えにくくなるため、保護者と学童の連携が大切になってきます。日々の様子を知らせてもらえるか、困ったことが合った際、気軽に相談できる体制があるかどうかも、信頼できる学童を見極めるポイントになります。日常的な情報共有を行ってくれる学童を選ぶことをおすすめします。
かちがわの杜は安全のサポート充実の学童保育
児童10名に対してスタッフ1名
かちがわの杜は、お子さんの安全性を高めるためにも少人数制でサポートを行っています。そうすることで、児童一人一人とのコミュニケーションを大切にし、発言しやすい環境づくりをしています。

最大20時までお預かり可能
かちがわの杜は、保護者の皆様名のご都合でどうしても基本時間ではない時間帯に利用したい場合に延長時間として最大20時までのお預かりを承っています。

![]() かちがわの杜
かちがわの杜 ![]()

かちがわの杜【春日井市の学童保育×習い事】
TEL:0568−37−3021
〒486-0931 愛知県春日井市松新町1−3
ルネッサンスシティ勝川一番街4F
Googleマップでルート案内
JR勝川駅(北口直結)より徒歩1分
教育付き学童保育(民間学童保育)
学童保育入所許可通知
放課後児童クラブ臨時利用許可(不許可)決定通知書
放課後児童クラブ・放課後子ども教室
—————————————–
春日井市 勝川駅前
教育付き学童保育かちがわの杜(民間学童保育)
TEL:0568−37−3021
かちがわの杜【春日井市の学童保育×習い事】
〒486-0931 愛知県春日井市松新町1−3 ルネッサンスシティ勝川一番街4F