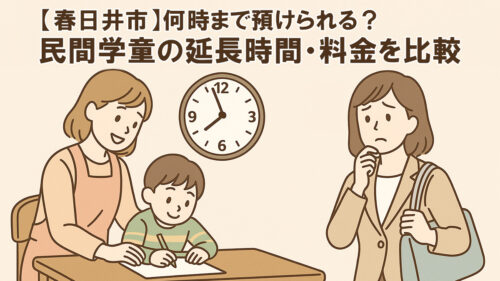学童では何をする?預かりだけじゃない、子どもの可能性を広げる活動内容を解説
2025年06月30日
共働き家庭が増える現代、小学生の放課後の過ごし方は、多くの保護者様にとって大きな関心事です。その選択肢の中心となるのが「学童保育」ですが、実際にどんなことをして過ごしているのかは、外からはなかなか見えづらいものです。
「宿題だけ?」「ただ預かってくれるだけ?」といった疑問を持っている方も多いでしょう。しかし、最近では“預かり”にとどまらない、子どもの成長を支える充実したプログラムを提供している学童も増えてきています。特に民間学童は、学び・体験・人間関係といった面で、家庭や学校とは違う「もうひとつの学びの場」へと進化を遂げているのです。
この記事では、「学童で何をするか」という基本的な疑問にお答えしながら、公立と民間の違い、そして子どもの未来につながる価値ある活動内容について、具体的な事例を交えながら詳しく解説します。
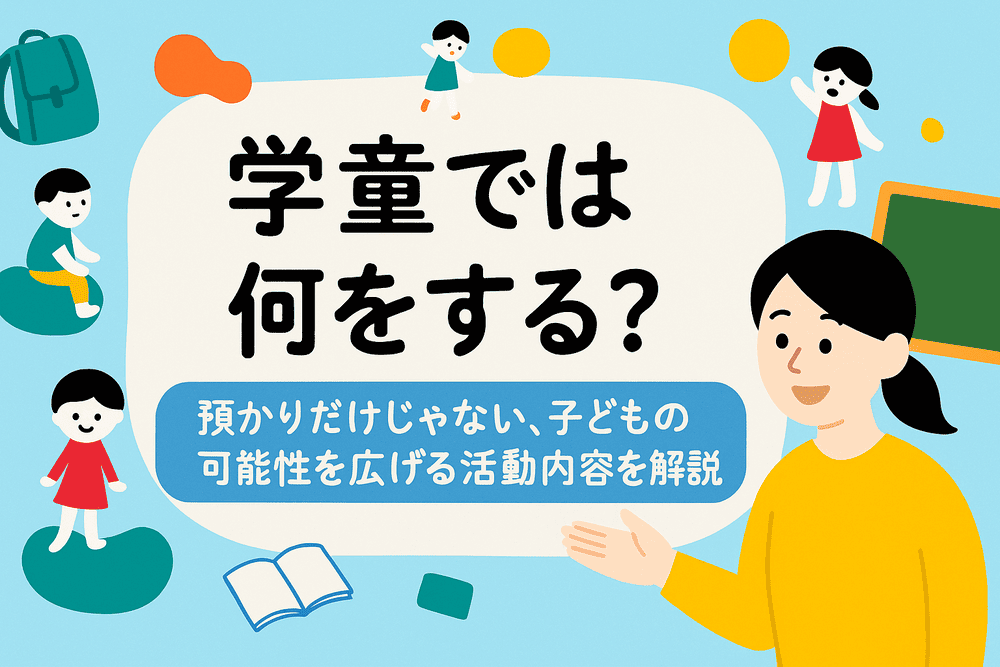
公立と民間でどう違う?学童保育の基本的な1日の流れ
学童保育の基本的な目的は、「保護者の就労などにより、放課後に家庭で過ごせないお子さんを安全に見守ること」です。まずは、一般的な公立学童の1日の流れを見てみましょう。
公立学童の特徴と一般的な過ごし方
公立の学童保育(正式には「放課後児童クラブ」)は、比較的リーズナブルな料金で利用できるのが大きな魅力です。多くの場合、小学校の敷地内や隣接した施設に併設されており、地域の子どもたちが集まりやすい環境が整っています。
- 14:00~15:00 下校後、施設へ移動
- 15:00~16:00 宿題・自習の時間
- 16:00~16:30 おやつの時間
- 16:30~18:00 室内や屋外での自由遊び
- 18:00~ 保護者のお迎え・順次帰宅
シンプルながら、学校と家庭の「間」をつなぐ大切な時間です。
学校からの距離が近く、安心して通わせやすい点や、地域の子どもたちとの交流が深まる点が魅力です。しかし、利用できる年齢や定員に制限がある場合が多く、指導員の数が限られているため、個別対応が難しいケースもあります。
民間学童の特徴と過ごし方の一例
民間学童の特徴は、ただ子どもを「安全に預かる」だけではなく、この時間を“学び”や“経験”の場として捉え、独自の教育プログラムを組み込んでいる点にあります。
- 独自の教育カリキュラムを導入し、学びと遊びを融合
- 習い事との連携により、移動の手間を省きながらスキルアップ
- 保護者への報告や面談体制が丁寧で、日々の成長を共有
- 送迎や延長保育が柔軟で、働く家庭をしっかりサポート
- 高学年まで対応:高学年になっても利用できる施設が多く、年齢に合わせたサポートを提供
【かちがわの杜のタイムスケジュール】
では、具体的な民間学童の例として、私たち「かちがわの杜」の1日の過ごし方をご紹介します。
学習・体験・遊びのバランスを大切にしたタイムスケジュールです。
学校開催時期(通常学童の例)

長期休暇(1日のお預かりの例)

※上記はあくまで一例です。日によって活動内容は異なります。
費用は公立に比べて高めではありますが、ただ時間を過ごすのではなく、
それに見合う“子どもの成長”と子どもが夢中になれる「何か」に出会える仕掛けを随所に散りばめています。
子どもの可能性を広げる活動内容
民間学童では、単なる“預かり”にとどまらず、学び・体験・人間関係づくりなど、子ども一人ひとりの可能性を広げる多彩な取り組みが行われています。
ここでは、さまざまな民間学童で実践されている活動内容をご紹介します。学童に「何を求めるか」によって選び方も変わります。ぜひ、お子様に合った環境を見つける参考にしてください。
子どもの可能性を広げる活動①|学びのプログラム
民間学童の大きな魅力が、「学びの質」です。学校の宿題サポートはもちろん、さらに一歩踏み込んだプログラムを提供しています。
- 探究学習・STEAM教育:答えのない問いに対し、自分で考え、調べ、表現する力を育むPBL(Project Based Learning)型学習。
- プログラミング・ロボット教室:論理的思考力や創造力を刺激し、これからの時代に必須のスキルを養います。
- 基礎学力の定着と向上:学校の宿題だけでなく、一人ひとりの習熟度に合わせた復習や先取り学習をサポート。わかるまで丁寧に指導します。
「勉強はつまらないもの」から「学ぶこと自体が面白い!」へと意識が変わることで、お子様の学習意欲に火をつけます。
子どもの可能性を広げる活動②|体験・創造・季節行事
多様な体験活動は、子どもの好奇心を刺激し、非認知能力を育む絶好の機会です。
- アート・工作:絵の具や粘土だけでなく、廃材を使ったアート制作など、創造力を解き放つ活動。
- 科学実験・クッキング:スライム作りやお菓子作りなど、化学変化や段取り力を遊びながら学びます。
- 季節のイベント:ハロウィン、クリスマス会はもちろん、日本の伝統文化に触れる七夕やお月見なども大切にしています。
机の上の勉強だけでは得られない、実体験を通した「生きた学び」が、子どもの世界を豊かに広げます。
子どもの可能性を広げる活動③|人間関係・非認知能力の育成
学童は、さまざまな年齢の子どもたちが集う小さな社会です。だからこそ、人間関係を築く力が自然と育まれます。
- 対話・発表の機会:自分の意見を伝え、相手の話を尊重して聞くトレーニング。
- チームでの活動:ルールを守り、仲間と協力して目標を達成する喜びを学びます。
- トラブルへの向き合い方:ケンカが起きた際も、大人がすぐに仲裁するのではなく、子どもたち自身が考え、解決する力を見守り、サポートします。
こうした経験を通じて育まれるコミュニケーション能力や協調性は、まさしく社会で求められる「生きる力」そのものです。
学童選びでよくある質問
ここでは、保護者様からよくいただくご質問にお答えします。
Q1. 夏休みや冬休みなどの長期休暇は、一日中預かってもらえますか?
A1. はい、公立民間ともに、長期休暇中の預かりに対応しているところが多いです。
一般的に民間学童のほうが預かり時間が長くなっています。
Q2. 習い事をさせたいのですが、送迎が大変です。
A2. 一般的な学童では、習い事に通わせる場合、保護者が直接送迎を行う必要があります。
「かちがわの杜」など、学習支援と習い事が一体化したワンストップ型施設の場合、施設内でそろばん・書道・プログラミングなどの習い事が完結するため、保護者様の送迎負担を大幅に軽減できます。
Q3. 急な残業や用事などで迎えが遅れる場合はどうなりますか?
A3. ほとんどの学童で延長保育の制度があります。延長可能な時間や、追加料金の有無、緊急時の連絡方法(電話、アプリなど)を事前に確認しておきましょう。
後悔しない学童選びのチェックポイント
学童を選ぶ際、「料金」や「場所」は重要ですが、それだけで決めてしまうのは少し待ってください。お子様の大切な放課後を任せる場所だからこそ、活動内容をしっかり見極めましょう。
- 公式サイトや資料で、具体的な活動内容が紹介されているか
- 宿題や自由時間以外に、独自のプログラムはあるか
- 見学時の子どもたちの表情はイキイキしているか
- 保護者との情報共有はどのように行われるか(連絡帳、アプリ、面談など)
実際に足を運び、「我が子をここで過ごさせたい」と心から思えるかどうかが、最も大切な判断基準です。
まとめ
学童保育は、もはや単なる「預かりの場」ではありません。
放課後の空き時間が、学び、体験、人との関わりを通して、学校だけでは得られない多様な力を育む「成長の時間」となり得ます。
愛知県春日井市の「かちがわの杜」では、学習支援・習い事・体験活動がひとつになった環境の中で、子どもたちの知的好奇心や「やってみたい!」という気持ちを大切に育んでいます。
体験会や短期のサマースクールも随時開催していますので、ぜひ一度、施設を見学したり実際に利用してみて、現代の学童保育の魅力を感じてみてください。
![]() かちがわの杜
かちがわの杜 ![]()

かちがわの杜【春日井市の学童保育×習い事】
TEL:0568−37−3021
〒486-0931 愛知県春日井市松新町1−3
ルネッサンスシティ勝川一番街4F
Googleマップでルート案内
JR勝川駅(北口直結)より徒歩1分
教育付き学童保育(民間学童保育)
学童保育入所許可通知
放課後児童クラブ臨時利用許可(不許可)決定通知書
放課後児童クラブ・放課後子ども教室
—————————————–
春日井市 勝川駅前
教育付き学童保育かちがわの杜(民間学童保育)
TEL:0568−37−3021
かちがわの杜【春日井市の学童保育×習い事】
〒486-0931 愛知県春日井市松新町1−3 ルネッサンスシティ勝川一番街4F